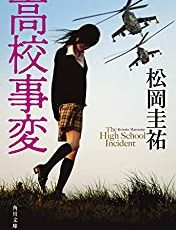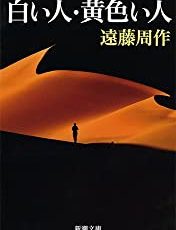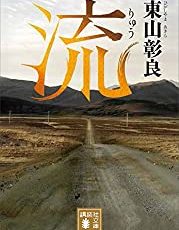あらすじ
1945年7月。ナチス・ドイツが戦争に敗れ米ソ英仏の4ヵ国統治下におかれたベルリン。
ソ連と西側諸国が対立しつつある状況下で、ドイツ人少女アウグステの恩人にあたる男が、ソ連領域で米国製の歯磨き粉に含まれた毒により不審な死を遂げる。
米国の兵員食堂で働くアウグステは疑いの目を向けられつつ、彼の甥に訃報を伝えるべく旅立つ。
しかしなぜか陽気な泥棒を道連れにする羽目になり――ふたりはそれぞれの思惑を胸に、荒廃した街を歩きはじめる。
(筑摩書房より)
感想レビュー
本屋大賞2019(第16回)第3位ノミネート、このミステリーがすごい!《2019年》第2位ノミネート
ずっと前から気になっていた作品の一つで、この機会に読むことができて良かったです。
まず読了後の所感としては「なんかすごい小説だったなぁ」というのが率直な気持ちですね。
読み進めるうちに、エネルギーというか、力強さをすごく感じる物語だったなと。
第二次世界大戦中や後のドイツを扱う作品って、映画とかも含めたら結構な数あるじゃないですか。
ユダヤ人側やソ連側から描いたり、また近隣国側や当然ドイツ側から描いたりと。
本作はそこから新たな切り口を見せてくれた作品で、また違った形でこの時代を考えることが出来ましたし、とても勉強にもなりました。
ちょうど読み終わりの余韻もあってか、タイトルもすごく良いんですよね、かっこいい。
物語の時代背景は、第二次世界大戦後にアメリカ、フランス、ソ連、イギリスに占領されたドイツが舞台となっています。
その中で、とある殺人事件が起きたのを皮切りに、主人公のドイツ人少女が、ソ連軍の依頼でとある人に会いにいく。
大筋としてはただそれだけなんですが、謎が多くて、そこから繰り広げられる展開が、簡単に予想できないような進み方をしていくんですよね。
幕間を過去編として、章ごとに挟み、徐々に物語の輪郭が浮き上がっていくような構成もハマっていました。
あと賛否両論あるかもしれませんが、当時の情景描写がとにかく凄まじいので、それにも脱帽しました。著者さんはこの時代に生きていたのか?と思わされるような臨場感でした。
それくらい、例えば著者名が隠されていたりすれば、この作品を日本人が書いたことが全く分からないようなクオリティの高さなんですよ。
解説にも書かれていたのですが、普通、こういう海外を描く作品って、少しでも自国の読者に共感をしてもらおうと(悪い意味ではなく)、自国味を足したりするものなんですよ。
文章や固有名詞なども、できるだけ自国民が読みやすいものにする。
でもこの作品は、本当にその真逆で、その国の人が書いたのだろうなと思わせるほどに、現地味をそのまま引っ張ってくるんです。
尖りとも言えるのかもしれませんが、私はこういった姿勢で物語が書ける作家が日本にいるんだなとすごく好感がもてました。
わかりやすく言うと、異国の風を感じたくて海外映画を見てるのだから、海外映画はやっぱり字幕で見たい派なんですよ、私は、笑
でも確かにそのせいで序盤とかは、説明や情景描写が多すぎて、テンポが悪いんですよね。
ただ最終的な結末の良さなどを考慮すると、この情景描写があるからこそ、この作品をより力強いものにしているのではないか、と思えるような面白さだったかなと思います。
こうして感想を書きながら思ったのが、現代作家でここまで当時の情景描写が書ける人ってかなり稀有な存在なんじゃないでしょうか。
今回、深緑野分さんの作品を読むのは初めてだったのですが、また機会があれば『戦場のコックたち』なども読んでみたいですね。
それでは今日はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事
合わせて読みたい
書店員が決める【歴代本屋大賞】全年度版ランキング!感想あり
合わせて読みたい
【歴代・全年度版】ミステリ界の頂点を決めろ!このミステリーがすごい!国内編最新ランキングまとめ