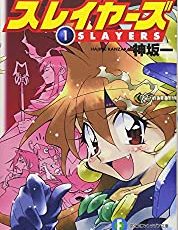あらすじ
まだ「何者」にもなれない「誰か」へ――
(ガガガ文庫より)
家に猫がいる者ならたいてい「うちの猫は特別だ」という。
だが彼とともにいた猫は本当に特別だった。
九年間、小説を書くときにはいつもそばにその猫がいた。その猫がいなければ小説なんて書けなかった。
彼は猫を飼っていたわけではなかった。ただ猫とともに暮らしていた。
感想・レビュー
まるでヒロインがいそうな雰囲気の表紙であるが普通にそうでもなかった。挿絵もない。
私はガガガ文庫のこういう作品たちをガガガ文庫尖りシリーズと呼んで、大変好んでいるのですが……。
さて、物語は所謂作家もので、中年の売れないラノベ作家・オフトンが、喋る猫・先生(お爺ちゃん)との会話が緩く続いていく。
どこか漱石の吾輩は猫であるかのような。
今まで読んできた作家ものとはどこか色が違う感じで、ヒロインもなしで派手な展開もない。
逆にそれが新鮮というか本来作家なんて地味な職業なのだからある意味真実かなと。
そして最後までオフトンが売れなかったのも物語を貫けた感があってよかったです。
だからこそ最後の先生に命を感じました。