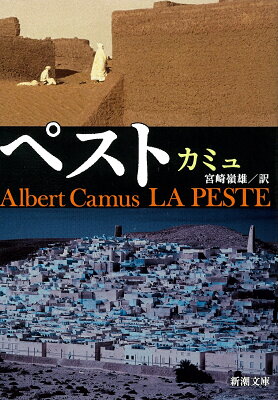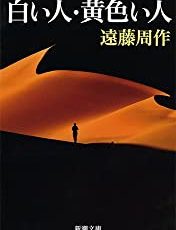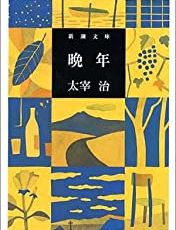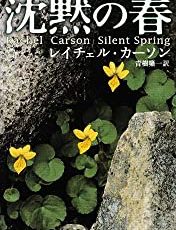あらすじ
アルジェリアのオラン市で、ある朝、医師のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの発生である。外部と遮断された孤立状態のなかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕む「不条理」と直面した時に示される人間の諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を呼んだ長編。
(新潮社より)
感想・レビュー
ノーベル文学賞受賞者であるアルベール・カミュの著書。
長かった。気づけば一週間くらい同じ本を読んでいた気がします。
物語はペストが蔓延してロックダウンされた街の人々を医師リウーが記述するという仕掛けで、全体的に寂しく静かな作品でした。
物語に起伏があまりなく、人間が持つ普遍性と感染されて死んでいく街を淡々と描く様はフランスのレジスタンス活動を比喩しているのか。
もしペストが収束したとしても終わらない労働や失った命、生活は帰ってこない無力感。何の為に明日を生きるのか。
流石に時代が今とは違い過ぎるので、こんなことを言うのもあれですが現代から見れば感染症対策や文明が発展途上に感じるが、一番は情報力の差が圧倒的に段違いですね。
だけど感染症に対する終わらない恐怖や失われた日常に対面した時の心は、時代が変わってもどうやら変わらないものらしい。
不条理といえばもう一人、カフカを思い出したが、カミュは社会という規模が大きい。どちらが良いとかではありませんが。