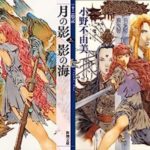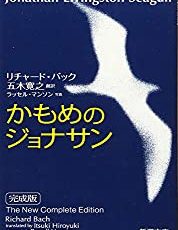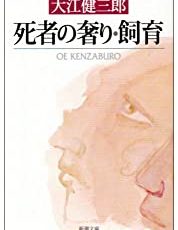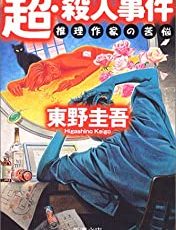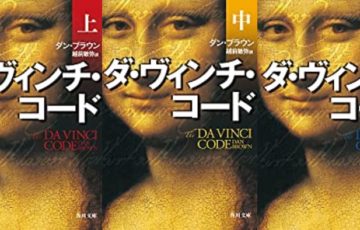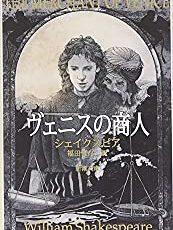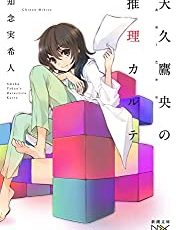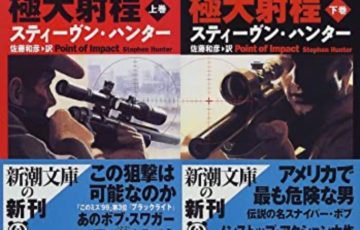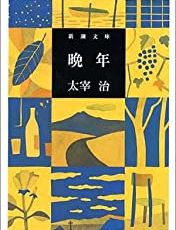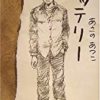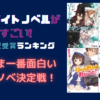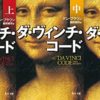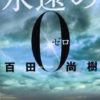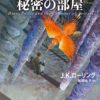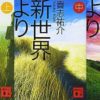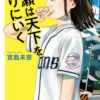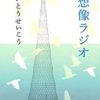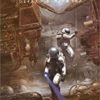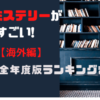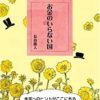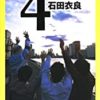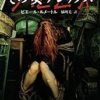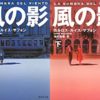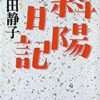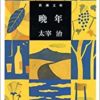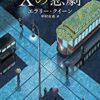(上巻)あらすじ
鋭敏な頭脳をもつ貧しい大学生ラスコーリニコフは、一つの微細な罪悪は百の善行に償われるという理論のもとに、強欲非道な高利貸の老婆を殺害し、その財産を有効に転用しようと企てるが、偶然その場に来合せたその妹まで殺してしまう。
この予期しなかった第二の殺人が、ラスコーリニコフの心に重くのしかかり、彼は罪の意識におびえるみじめな自分を発見しなければならなかった。
(新潮社より)
(上巻)感想・レビュー
ドストエフスキーは初読みになります。
まさにパワー、エネルギーを感じる作品でした。
貧しい大学生が犯した絶対正義の殺人のはずが予期せぬ事態にその妹にまで手をかけてしまい、少しずつ歯車が狂いだす。
序盤の殺人から、ひたすらに内面葛藤があり終盤辺りでまたエグい程に引き込んでいくこの力量。
さすが巨匠。あと所々笑えるユーモアもあります。
これが1860年代ロシアの雰囲気なのか、若者の狂信的な一面が生々しくここまで内面を掘り起こした作品には出会った事がない。
今の時代ではまどろっこし過ぎて、中々お目にはかかれないと思う。
心理的にも犯罪捜査的にもまだ発展しきれていないから生まれる葛藤なのでしょう。

(下巻)あらすじ
不安と恐怖に駆られ、良心の呵責に耐えきれぬラスコーリニコフは、偶然知り合った娼婦ソーニャの自己犠牲に徹した生き方に打たれ、ついに自らを法の手にゆだねる。
――ロシヤ思想史にインテリゲンチャの出現が特筆された1860年代、急激な価値転換が行われる中での青年層の思想の昏迷を予言し、強烈な人間回復への願望を訴えたヒューマニズムの書として不滅の価値に輝く作品である。
(新潮社より)
(下巻)感想・レビュー
ようやく下巻も読了。
素直に面白かったです。これがドストエフスキーか。
ラスコーリニコフが犯した殺人という罪に対し、罰などいるのだろうか。
いっそこのまま可愛い妹や心配性の母と信のおける友人とソーニャと共に平穏に過ごす事は出来ないのだろうか。出来ないのだろう。
彼の良心はいつだって苦痛の苛責を続けるし、心の奥底でそれを望まない。
19世期ロシアの若者でなくても、形は違えどロージャと重なる部分が多くの人にあるから支持され続けているんだと感じました。
内容が濃く整理するのにもう少し時間が必要ですが、読んで良かったです。
ラストは不覚にも感動しました。最後の河岸に漂う哀愁。
ラスコーリニコフに寄り添うソーニャ。罪と罰。更生と愛。
それらはいまも私の脳内に強く焼き付いています。
今振り返ってもやはりこの作品は唯一無二だったな、と思っています。