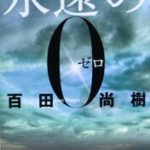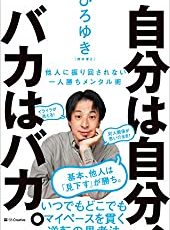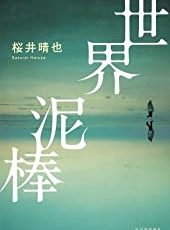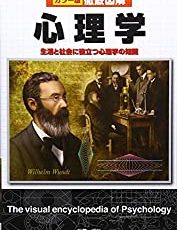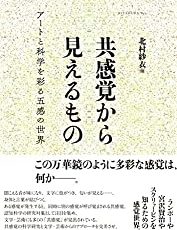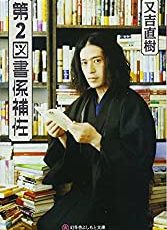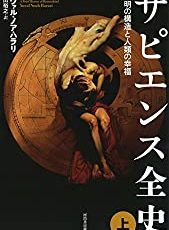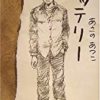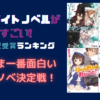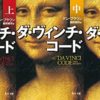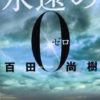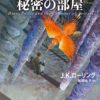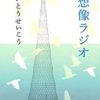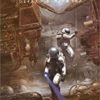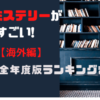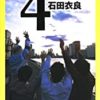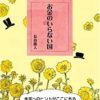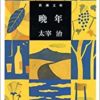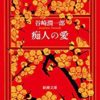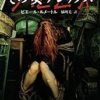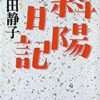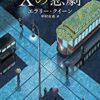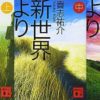あらすじ
世界をまたにかけて移動し、世界中の人々に影響を与え続けているユダヤ人の起源から現代までの三千年以上にわたる歴史を、簡潔に理解できる入門書。
各時代における有力なユダヤ人社会を体系的に見通し、その変容を追う。
オックスフォード大学出版局の叢書にもおさめられている基本図書。多数の図版と年譜、コラムを収録。
(河出書房新社より)
感想・レビュー
著書:レイモンド・P・シェインドリン 翻訳:入江規夫
まず本書では「ユダヤ人の歴史の古さと長さを手際よくまとめるのは不可能である」と最初に語られています。
それでも文庫本サイズ約360頁に文字数はびっしりとありますが、私のような無知な人間にはとてもわかりやすく書かれていたように思えます。
巻末にはユダヤの歴史年表まで添えてあり、とても参考になりました。
本書では、3000年以上という長い長いユダヤ人の歴史を追っていきます。
現在起きている(2023年)『ハマスとイスラエルの衝突』にも繋がっていきますので、この機会に改めて知っておいて損はないかなと思います。
その前にまず読了後の所感としては「何なんだ、この呪われた一族は……そして何なんだ、この愚かな人間たちは……」と、本当になんて言っていいのか分からなくなるような、虚しさを覚えました。
同時にこれが反射的創作能力を持ってしまったホモ・サピエンスの限界であり、遠い未来、我々も同じように未来人たちに思われることなのだろうなと。
まず本書は第十一章までありますので、ある程度年代も区切られて書かれていました。
以下、参考までに。
- 第一章「古代イスラエル人の起源とその王国」(紀元前1220年以前〜紀元前587年まで)
- 第二章「ユダヤの地とディアスポラの起源」(紀元前587年〜紀元70年まで)
- 第三章「ローマ帝国下のパレスチナとササン朝ペルシアのバビロニア」(紀元70年〜632年まで)
- 第四章「イスラム社会におけるユダヤ人/イスラムの勃興と中世の終わりまで」(632年〜1500年まで)
- 第五章「中世キリスト教ヨーロッパ社会におけるユダヤ人」(9世紀〜1500年まで)
- 第六章「オスマン帝国と中東におけるユダヤ人」(1453年〜1948年まで)
- 第七章「西ヨーロッパのユダヤ人」(1500年〜1900年まで)
- 第八章「東ヨーロッパとアメリカ合衆国のユダヤ人」(1770年〜1940年まで)
- 第九章「ホロコースト」
- 第十章「シオニズムとイスラエル建国」
- 第十一章「一九四八年以降のユダヤ人」
他、あとがきや歴史年表、章ごとにコラムなども掲載されていて、そちらも興味深い内容でした。
まずユダヤの歴史は、古代イスラエル、カナンからはじまります。私からすれば本当に聖書の中の世界って感じで、旧約聖書のモーセの辺りとかになってくるんですよ。
そこからローマ帝国に入っていき、今後のユダヤ人の歴史を左右するような出来事が起こっていきます。
紀元1世紀辺りの、聖地エルサレムやローマ文明とユダヤ人たちの関係性がすごく理解できて、助かりました。
むかしこの頃のローマの特集をテレビでぼんやり観ていた記憶がありますが、恥ずかしながらあまり覚えておらず、カリギュラからネロ・クラウディウスの辺りの背景に、ユダヤの怒りがここまであるとは知らなかったです。
あとこの頃にキリストの処刑があったのは有名ですが、一つ興味深いことが書かれていて、この時代の磔などの刑は珍しいことではなく、キリストの処刑もその幾つもある刑の一つに過ぎなかった、という点です。
その後、キリストの復活が起きて、徐々にユダヤへの敵視は広がっていきますが、確かに前提として、この頃にはユダヤ教しかなく、キリスト教という宗教はありませんよね。
でもここから20数人くらいしかいなかった信者が、長い時間をかけて世界中に膨れ上がってしまうのですから、やはり聖書(物語)の力は侮れないです。
他にもキリスト教は、ユダヤ教の面倒な儀式などをなくし、誰でも神を信じる気持ちがあればオッケーという寛容的なスタイルにし、布教を絶やさなかったのも大きいとは思いますが。
あとは結果が全てだとでも言うように、ローマ時代のキリスト教信者などが、農作などの為に奴隷を雇い繁栄したの対して、奴隷を拒んだユダヤ教がこういった運命を辿るのは、皮肉な世界だなとも思いました。
話を戻しまして、次にユダヤ人は世界に拡散というか、追い出されるように広がっていきます。
ここから貧困、迫害、差別、虐殺などが長い長い時間をかけて起き続けます。
細かいところは、歴史年表を見るなり、それが起こった背景を知りたい場合は本書や、他の専門書を読むしかないです。
それくらいユダヤ人の身に起きた災難というか、悪夢のような出来事が多すぎます。
目や耳を塞ぎたくなるような現実かもしれないですが、それを行ったのは、我々と同じ直立二足歩行の人間なのですから、しっかりと学んでいきたいところです。
それが歴史の必要性であり、善悪構造論などは一旦抜きにして、改めてそう感じましたね。
ホロコーストが終わり、終盤はイスラエル建国からアラブ諸国周辺地域の争い、関係性や事情などが、書かれていました。
過去のユダヤ人の歴史を叩き込んだお陰で、より理解しやすくなったかなと思います。
これにより、現在のイスラエル問題にも繋がってくるのですが、この争いは、ニュースなどで流れるイスラエル建国からの問題を知ってもちょっと理解が難しいだろうなとも思いました。
その背景にあるユダヤの長い3000年の歴史を知らなければ、そもそもここまで人間同士が戦っている意味が分からないだろうなと思います。
特に現代に生きる私のような人たちにとって。
まとめ
本書を読んでユダヤを知るということは、改めてキリスト、イスラムを知ることに繋がるのだなと思いました。
ずっと気になっていたキリスト教に旧約聖書(ユダヤ教)がある意味がよくわかりました。
あらゆる神々を認める寛容の時代から、ユダヤ教の特徴である「他の神は認めない」という一神教の教え、預言のような内容、その不寛容さを上手く利用した形にもなっていたのですね。
あとは一時期、殆ど誰も使わなくなったヘブライ語の復活は、言語の歴史としてもかなり珍しい例だそうですね。とても勉強になりました。
それにしてもここまで長い間、宗教的分けられ方をした人間の種族、一族って他にないですよね。私が無知なだけかもしれないですが。
普通に考えたら仏教人やキリスト人イスラム人として3000年以上迫害にあうってことですもんね。
いくら古代に王国があり、アンティオコスを含めた迫害的政策が多数あり、それでもヤハウェの教えを頑なに守り続けると言っても、まぁ当時の世界の常識を考えると確かに浮いて見えるかもしれませんが、それでもナチス・ドイツのホロコーストまで続くって少し異常じゃないですか。
この頃はもう国も情報量も古代とは、わけが違うのですから。それでも遺伝子的、歴史的に残ってきた呪いとでも言うんですかね。
ただ最後に思ったのは、歴史って繰り返すってよく言うじゃないですか。私も今までそう思って生きてきたのですが、ちょっと違うのかなって。
自分たちの時代は、こんなにも賢くなったんだから、昔と比べてこれ以上悪いことは起こらない、と無意識に思いこみ、人類は賢くなる度に、昔以上の悪いことを起こし続け、更新してきたんですよね。
だから、賢くなって、世の中が便利になった時、歴史は繰り返すのではなく、過去を上回る悪い出来事が起こると思っておいた方がいいのかもしれません。
いまのところこの歴史の法則は決して外れず、必ずそうなってきました。世界は産業革命以降、生産性が向上し、爆発的に人口は増え続け、二次大戦という最悪を更新しました。
最悪を更新して月日が流れ、さらにここ数年、また戦争が各地で起きはじめている。
それで人の数って同時に死の数でもあるんだな、と思いました。
色々考えさせられる一冊ですね。それでは今日はここまで。
ぜひ興味ある方は、ユダヤ人の長い歴史を追ってみてはいかがでしょうか。私もまた別の本を読んでみようと思います。
それではまた。最後までお読みいただきありがとうございました。