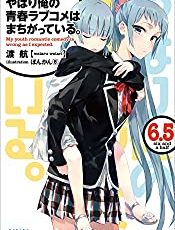あらすじ
栗原一止は、夏目漱石を敬愛する信州の内科医だ。「二十四時間、三百六十五日対応」を掲げる本庄病院で連日連夜不眠不休の診療を続けている。四月、東京の大病院から新任の医師・進藤辰也がやってくる。一止と信濃大学の同級生だった進藤は、かつて“医学部の良心”と呼ばれたほどの男である。だが着任後の進藤に、病棟内で信じがたい悪評が立つ。失意する一止をさらなる試練が襲う。副部長先生の突然の発病―この病院で、再び奇蹟は起きるのか。
(小学館より)
感想・レビュー
第八回本屋大賞第8位ノミネート。
前巻を読んでとても感動したので、続編を読んでみました。
まず読後すぐの所感としては、文章というか文体の運び方、会話文のリズム感が前巻(神様のカルテ感想)と比べてとても良くなったなぁという印象ですかね。
内容も十分に面白かったです。
では感想の方をぼちぼち書いていきます。
前巻も一応綺麗に終わっていたのと、そこまで何か大きな伏線があったわけでもないのでどうやって物語を作っていくのかなぁというところ。
まずは漱石文体と、長野の山岳描写は相変わらずと言いますか、読んでいてもその美しき緑や自然が伝わってきますし、この辺も全体通して前巻より洗練されていたかな思えました。
そして主人公・栗原一止の医大時代の同期・進藤が同じ病院にやってきます。そこで一止の過去などが徐々に明かされていきます。
初めて明かされる三角関係という一止の淡い初恋や、学生時代の進藤などの掛け合いなども非常に面白く読めたかと思います。
そして物語は進藤の働き方についてトラブル(親として医者としての在り方)が起きたり、前巻から登場している古狐先生(医者として、一人の人間としての家族)の話など、縦軸と平行して副題が横軸で動いていくスムーズな構成のながれ。
色々と医者ではない人でもつい考えてしまう副題は、ベタと言えばベタですが、現代社会の働き方の方向性に沿っていて、だが医者という特殊な仕事を加味して読むことで奥深い難題へと様変わりする。
私の母も看護師なので、夜勤もよくありますから、余計に共感できた部分もあったかもしれません。
あとは医療が題材の作品にはつきものでもある、死の数の多さ。これも昔母親からよく聞かされた色々懐かしい話をついつい思い出したりしましたね。
私的には、前巻ほど感動して涙する展開はなかったものの、細君のハルさんとの関係性や、美しい自然描写も含めてじんわりと楽しめた一冊だったと思います。
古狐先生の話はどうしても悲しくなるところを、敢えて屋上のシーンを作り、方向性を優しい向きに変えたのも良かったなぁと思えましたね。
感想はこの辺で、今回この作品を読んでやっぱり医者という職業は、とても複雑だなと思いました。
医者である前に、まず一人の人間であるし、でも医師免許を取得して医者になるにはとても難しい。
だから人手不足は免れないし、必然的に労働環境は悪くなる。またそれを無理に解消しようと医者になるのが安易になってしまうとその分だけ事故も起きる。
うーん、難しいなぁ……
合わせて読みたい
書店員が決める【歴代本屋大賞】全年度版ランキング!感想あり